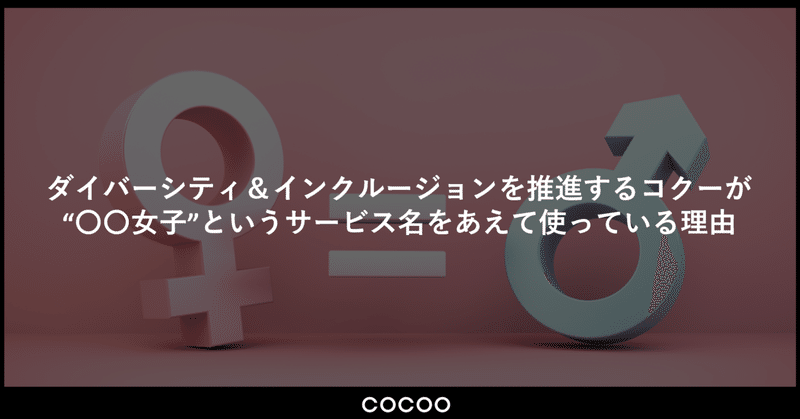みえる!コクー|コクー株式会社
コクー株式会社のオープン社内報「みえる!コクー」。
『デジタルの力でダイバーシティー&インクルージョンがあたりまえの社会を創る』をパーパスに掲げるコクーの365日が見える!社内報です。~みて知って、もっとコクーが好きになる~ をコンセプトにお届けします。
記事一覧

月1回開催の社内イベントで部門を越えた社員の交流を目指す!~2023年6~12月のイベント振り返り~【コクーの社内コミュニケーション⑤】
皆さん、はじめまして! コクー株式会社 イベント班の"ゆう"です。 イベント班の前回の投稿から約1年が経ち、今回はまた更にパワーアップしたイベント班の活動をお届けしたい!とワクワクしながら記事を書いております。 ▼イベント班とは?はこちらの記事をご覧ください 私が思う個人的なイベント班のやりがいは参加者の方からの「参加してよかった」の声をいただけることです。 毎月行う定例ミーティングや各々に振り分けられているタスクの数々… 自身の業務と並行しながらは正直大変ですが、「

企業と地域をつなぐ「ふくしまCOLLABO」のワーケーションに参加~地域交流での体験を通して"ふくしまの食を学ぶ”1週間~
こんにちは。マーケティング部の"熊さん"です。 今回は社内で参加者を募り、2月にコクー社員4名が参加した、ふくしまワーケーションプロジェクト「ふくしまCOLLABO(コラボ)」についてレポートします! 「ふくしまCOLLABO」ワーケーションプロジェクトとは?福島県は、首都圏企業と県内地域との接点をつくり、新たな人の流れを創出することで「転職なきふくしまぐらし」のモデルケースを創出・拡大したい、という目的のもとで、ワーケーションプロジェクトを実施されています。 滞在してワ